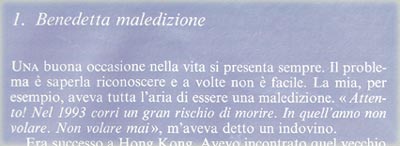→プリント用バージョン 1. Benedetta maledizioneありがたい不吉な予言 人生のチャンスというものは、いつも目の前にある。問題はそれがチャンスであることに気づくことができるかどうかであり、時にむずかしい。たとえばわたしの場合、それは不吉な予言としか思えないものだった。「気をつけろ!1993年、死の大きな危険がお前を襲うだろう。その年、お前は飛んではいけない。絶対に飛ぶな」――ある占い師にわたしはそう言われたのである。 香港でのことだった。その老中国人と出会うことになったのは、まったくの偶然からだった。老人の言葉にその時は当然驚いたものの、たいして気にかけることもなかった。まだ1976年の春で、問題の1993年ははるか先に思えたから。だがその期限だけは忘れることがなかった。まだ行こうかどうしようか決めていない約束の日付けにも少し似て、それは頭のなかにのこっていた。 1977年……1987年……1990年、1991年。十六年は長く思える、特にその最初の一日から眺めたならば。だが、思春期を除くあらゆる年月と同じく、この十六年も疾く過ぎゆき、あっという間に1992年の年末となった。さて、どうしたものか。かの老中国人の言葉を真に受けて、忠告に従い、人生の再計画を試みるべきか。それとも何もなかったことにして、「占い師どもの戯言など、くそ喰らえ」と心の中でつぶやきながら、今まで通りに前進を続けたものか。 ↓down わたしはそれまで二十年以上、ずっとアジアに暮らしてきた。まずシンガポール、そして香港、北京、東京、最後にバンコク。そこで、「予言」に対応する手段もアジア流が最適であろうと思い至った。つまり、「さからわず、服従する」である。 「すると君は、予言を信じているのか?」そう問いかけてくる同業のジャーナリストたちに、わたしはいらだたせられることになった。とくに欧米のジャーナリストたちだ。彼らはどんな疑問にも常に、イエスかノーかの明確な解答を欲することに慣れ切った人々であり、このような答えにくい質問をするときですら、その姿勢が変わることはない。人が曇りの日にカサを持って家をでるのは、天気予報を信じたからだとは限らない。雨降りは一つの可能性であり、雨傘は一つの予防策なのだ。 なぜ、運命に逆らわなくてはならないのか。運命が自分のために何かを予兆し、ヒントをくれようとしている時に?ギャンブルのルーレットで黒の目が三、四回続けて出ると、確率の計算から持ち金をすべて赤に賭ける者たちがいる。だがわたしはちがう。もういちど、黒に賭ける。そうさせるためにこそ、ルーレットの玉はわたしにウィンクしてくれたのではないだろうか。(p10) それに、まる一年飛行機にのらないというアイデアそのものが、わたしは気に入っていた。なにより一つの挑戦として。一人の香港の老中国人がわたしの未来の鍵を握っている、そう思いこんでみるのはとても愉快だった。未知なる土地への第一歩を踏み出すような気分でもあり、その歩みがいったいわたしをどこへ連れて行ってしまうのかに興味があった。いずれにせよ、それがわたしをいつもとは違った生活に、しばらくの間、いざなってくれることはほぼ間違いなかった。 もう何十年もわたしは飛行機で旅をしてきた。戦争や革命、大惨事が発生している世界で最も苦悩に満ちた場所の数々を仕事のために訪れるうちに、息のとまるような思いをしたことも当然ながら幾度もあった。エンジンの一つを炎上しながらの着陸もあれば、まさに墜落直前、技師が座席の間に開いた上げぶたの中をカナヅチで一撃し、飛行機の腹から出ることを渋っていた車輪をなんとか引っ張りだしての着陸などもあった。 空の上で長い時間を過ごしてきた人であれば、パイロットを含めて、誰もが遅かれ早かれ悩まされることになるあの不安。もし1993年にあの予言を無視して、何ごともなかったかのように飛びつづけていたならば、わたしはそんな落ち着かない気分を新たに1ダースは抱かされることになったに違いない。そして、それでもやはり、「飛行機→タクシー→ホテル→タクシー→飛行機」といういつものルーチンを相変わらず繰り返すことになったことだろう。 あのお告げはわたしに、人生のバラエティーを豊かにする機会をあたえてくれるもの、いやむしろ、そうすることを命じるものだったのだ。 予言は言い訳だった。本音を言えば、五十五歳の男と言うものは自分の人生に詩情をちょっぴり加えたくなるものであり、世界を新たな目で眺めてみたくなるものであり、古典文学を読みなおしたり、陽が昇ること、空には月があること、時間とは時計が小刻みにしたものだけではないことを再発見してみたくなるものなのだ。これはわたしに与えられたチャンスであり、見逃すわけにはいかなかった。 問題はそれをどう実行するかということだった。仕事を一年間なおざりにするか、長い休暇をとるか、それともこの制限のなかで何とか仕事をつづけるか。他の職業と同じく、いまやジャーナリズムの世界もIT化の波に支配されてしまっている。そこではコンピューターにモデム、そして速度が主役をつとめている。衛星で送られてくるテレビ映像の短さとタイミングの良さは、新たなスタンダードを築きあげた。そうした時、印刷媒体のジャーナリズムは、時間をかけた考察と書き手の個性に重きを置くべきところが、とうてい勝ち目のないテレビの即時性をまねようとその後を追いかけることしかしていない。テレビの即時性とともに、その表面的な報道をも模倣しながら。(p11) 天安門で虐殺がおきていた日々、北京の中心にあるその広場からCNNが現場中継をしていた。わが同僚たちの多くは、ほんの数百メートル先で起きている事件を自分の目で見に向かうよりも、ホテルの部屋でテレビの前にいることをよしとした。最新情報を逐一キャッチし事件の展開を追うためには、それが最も速い手段だったからだ。加えて、彼らの上司に編集長たちも何千キロも離れた場所で、やはり同じ映像をテレビで見ていた。こうしてその映像が唯一の真実となった。他の真実を探しにゆくことなど、無駄なことだった。 個人的な気まぐれのために一年間飛ばないと決心した海外特派員をアジアに一人持つことになると知ったら、わが上司たちはどんな反応を示すことだろう。戦争勃発の知らせを受けて現地に向かい、しばしばそれが終結してからようやく現地に到着していた二十世紀初頭のジャーナリストたち。1993年に、いきなり一昔前のジャーナリストになってしまうわたしのことを彼らはどう思うだろうか。 それを確かめる機会は1992年の10月にやってきた。「デル・シュピーゲル」誌の二人の編集長のうちの一人がバンコクにやって来たのだ。ある晩、彼と夕食をすませたあとで、わたしは単刀直入に香港の占い師のエピソードを語り、1993年は飛行機にのらないつもりであることを説明した。 「あなたの口からそう聞かされたあとで、次のクーデターが起きた時マニラに飛べとか、次の台風が来た時バングラデシュに飛べなど、言えると思いますか。自分がいいと思うようにやってください。」――それが彼の答えだった。いつも通りじつに素敵な、遠く離れた我が主人たち!二人は、わたしのわがままから何か変わった物語が生まれるかもしれないこと、そして、ほかの誰も持っていない何かを読者たちに提供できるだろうことを理解したのだった。 「デル・シュピーゲル」の反応に当然ながらわたしの気分はすこし軽くなった。だからと言ってすぐさま決断を下したわけではなかった。「予言」の内容は次の年の始まりとともに有効になるものであったから、わたしは最後の瞬間に、つまり大晦日の真夜中の鐘が鳴る時に、たとえ自分がどこにいようともそこで決断をすることにした。決断の時、わたしはラオスの森のなかだった。大晦日の晩餐は赤アリの卵のオムレツだった。乾杯のためのシャンパンはなかったが、わたしは新鮮な水のコップをかかげて、いかなる事情があろうとも飛ぶ誘惑に決して負けないことを正式に誓った。こうしてわたしは、飛行機・ヘリコプター・グライダー・ハングライダーを除く、可能な限りのあらゆる交通手段で世界を旅することになった。 それはじつに素晴らしい決断であった。おかげで、一九九三年はわたしの人生の中でも、最も偉大な一年のひとつとなることになったのだから。そこで死ぬはずであったわたしは、逆に生まれかわることになった。不吉な予言とみえたものが、実は真の幸運のお告げであったことが明らかになったのである。(p12) アジアとヨーロッパの間を列車で、船で、車で、時には足で移動しているうちに、わたしの日々のリズムはそれまでとは完全に異なるものとなった。距離はその本質を取り戻し、わたしは旅にかつてのような発見と冒険の楽しみをふたたび見いだした。 空港にかけつけ、クレジットカードでチケットを買い、さっさと飛び去り、あっというまに、正にどこにでもたどり着く可能性を失ったことで、わたしは突然、世界を、渡るべき多くの海峡・越えてゆかねばならぬ多くの河川・それぞれビザが必要な国境に分断されたさまざまな国々が複雑にからまったものとして見直さざるを得なくなった。そのビザにしても特別なもので、「陸路経由」と明記されてなくてはならない。それはまるで特にアジアではこの経路があまりに異例なものとなったが故に、そこをあえて通ろうとするものは自動的に猜疑の対象になるといわんばかりである。 移動はもはや何時間単位の問題ではなく、何日、何週間単位で計算するものとなった。まちがいを避けるため、旅を始める前にわたしはそれぞれの地図を眺め、地理をもう一度あたまに入れる必要があった。山脈はふたたびわたしの歩みを妨げうるものとなり、もはや飛行機の小窓から見おろした時のような、風景を彩るちょっとした美しい飾りではなくなった。 長距離をゆく列車や船の旅のおかげで、わたしは世界の広さをあらためて実感することになり、そしてなにより、ある種の人間たちを再発見することになった。空を飛んでいるうちにその存在すら忘れてしまうものの、じつは全人類の過半数を占める人々のことだ。それは荷物や子供たちを満載して移動する人間たちであり、飛行機と彼ら以外の人々がみな、あらゆる意味で頭上を飛び越えて行ってしまう者たちのことである。 飛んではならないという強制は、驚きにあふれたゲームとなった。短い時間だけ盲目になったふりをしてみると、視覚を失うかわりに他の感覚が鋭敏になることに気づく。飛行機の拒絶もそれと似たような効果がある。列車はその時間的余裕と空間的制限をもって、普段は使わなくなっている物事の細部への好奇心を人によみがえらせ、まわりにあるものや車窓を流れゆく風景への注意力を鋭敏にする。飛行機の上では、人は遅かれ早かれ何も眺めず、耳をふさぐようになる。そこで会う顔はいつも同じだし、会話の内容も話す前から分かりきったものだから。列車の上では、すくなくともアジアの列車の上では、話は別だ!そこで同じ日々を分かち合い、食事も退屈さも共にすることになる彼らは、別の場所では決して会うことのないだろう人間たちであり、その中でも強い個性をもつ人物たちはいつまでも記憶に残ることになる。(p13) 飛行機なしでやっていくと決めた途端に人は、飛行機が普段いかに限定的な世界観をわたしたちに押しつけているかということに気づくものだ。距離を省略する快適な早道であることで、飛行機はあらゆるものを短縮してしまう。世界というものに対するわたしたちの理解までも。夕暮れ時にローマを発ち、夕飯を食べ、すこし寝て、日の出の頃にはすでにインドについてしまう。だが、ひとつひとつの国はそれぞれ全く異なったものであり、ある国を訪れる者はそれと対面する心構えをする十分な時間を持つべきであり、征服の悦びを得るためには、まず苦労をしなければならないものなのだ。今日では何もかもが余りに簡易になってしまっていて、そこには何の喜びもない。何かを理解することは楽しい。ただそれが楽しいのも、まず何らかの努力があってからの話である。世界の国々の理解についても同じことが言える。空港から空港へと飛びながらガイドブックを読むのと、列車に乗った旅人が地面から離れることなく、その地のエキス(土地柄)を――浸透力によって――ゆっくりと、困難を重ねて吸い込んで行くのとは全く別の話しだ。 最低限の努力もすることなしに空路で到着した者の眼には、どの場所も同じように見えてしまう。どこもかしこも、数時間のフライトで隔てられた単なる目的地のひとつにすぎない。国境というものは自然環境と歴史によって明示され、それに囲まれてくらす民の意識の中にしっかりと染み込んでいるものであるが、空港のエアコンが効いた真空管の中から発着する者にとっては、それも本来の価値を失い、存在しないも同じことになってしまう。空港とは、コンピューターを前にした一人の警官が「国境」であり、荷物を運び出すベルトとの遭遇が未知との遭遇であり、今やどこでも同じになったデューティーフリー・ショップを通過する強制的な順路のかきたてる欲望に惜別の感動が乱される、そんな場所である。 船は慎み深くゆっくりと河口に入り、目的の国へと近づいてゆく。遠くにあった港は、他のどこにもない唯一の顔とにおいをもって、あこがれの到着地へと姿を変える。一昔前、飛行場(i terreni di aviazione)と呼ばれていたものも少しそれに似ていた。今はちがう。今日の空港は広告の文句のようにニセモノであり、たとえそこの国家が崩壊状態であってもわりと完全な状態を保つ島々であり、世界中どこでもそっくりだ。またどこの空港も同じ国際共通語を話し、たどり着いた旅客の誰もにまるで故郷に帰ってきたような印象を与える。だが実際のところ彼らは、どこかの町の郊外に到着しただけであり、そこからバスやタクシーに乗って中心街を目指しふたたび旅立たなければならない。そして、中心街は空港からえらく遠くにあるのが常である。 だが、鉄道の駅はそうではない。駅は本物であり、町の中心にあり、その町を映し出す鏡である。(p14)駅は大聖堂のそばにあり、モスクのそばにあり、パゴダや霊廟のそばにある。駅につけば、人は真にどこかに到着したことになるのだ。 飛ばないというこの制限にもかかわらず、わたしは自分の職務を放棄することはなかったし、行かねばならない場所には、カンボジアの初の民主選挙からビルマ経由のタイ・中国間の初の陸路(!)連絡ルートの開通まで、つねに遅れることなくたどり着くことに成功した。 夏には、慣例の年間行事である母を訪ねてのヨーロッパ訪問もきちんとこなした。それは「歴史的な」バンコク発フィレンツェゆきの汽車の旅となり、カンボジア・ベトナム・中国・モンゴル・シベリアを経由する二万キロの道のりであった。その旅自体は驚異的でもなんでもないものだ。ただ、もう長いこと誰もそこを行く者が居なかったという点を除けば。車輪と枕木が奏でる打撃と反動のリズムと、さまざまな国の機関車の汽笛のテンポにのって、地図の上では世界のちいさな一部分にしか見えない土地を横断する一ヶ月の旅であった。 ヨーロッパからの復路、こんどは妻のアンジェラとともにラ・スペッツィア( 訳注:イタリア北西部、リグリア州の港町) からロイド・トリエスティーノのおんぼろ船にのりこみ、地中海からスエズ運河・紅海・インド洋・マラッカ海峡、そしてシンガポールにいたる、壮大で、クラッシックな航路をゆくことになった。乗客はわたしたち二人だけだった。あとはコンテナが二千個に、極め付けにイタリアンな18人の乗組員たちがいた。 もしも例の占いの言い訳を思いつかなかったら、わたしはこれらの出来事の一つも経験しなかっただろうし、1993年はこれと言って印象にのこる出来事もない、ありきたりの一年となっていたに違いない。 一人のジャーナリストは一生の間にいったい何度、歴史的瞬間に出くわすことができるものだろうか。二回あれば、幸運な方だ!わたしは、自分の幸運の配分をすでに受け取ってしまっている。まずは1975年の春、サイゴンで。北ベトナムの共産党軍がやって来て、戦争が終結した。あの戦争はわたしたちの世代にとって、ヘミングウェイとオーウェルの世代のスペイン市民戦争のようなものであった。それから、1991年の夏わたしはソビエト社会主義共和国連邦の腸の中にいた。そして、その時ソ連帝国が崩壊し、共産主義が死を迎えた。(p15)本当に運が良ければ、またいつの日か大きな歴史的事件の証人になることが出来るかもしれない。だがそれまでわたしは、どんなに地味で話題性に欠ける事件に対しても、自分の好奇心を磨いておく必要がある。 飛ばないという決意とともに、わたしはこのゲームの論理的帰結であるもう一つの決意をした。この一年間どこに行こうともそこでわたしは、土地で一番有名な占い師、最強の魔術師、一番人気のある聖者、さらには易者、狐憑き、狂人に会いにゆくことにしたのだ。自分の運命を知るために、そして彼らにわたしの将来をひとめ覗いてもらうために。 必然的に、わたしはありとあらゆる種類の予言をきくことになった。ひとつひとつの出会いが新たな冒険であり、道をすすむにつれ、さまざまなオイル・護符・丸薬・粉末・数々の危険から逃れるためのそれぞれの処方せんなどと一緒に、予言や生き方のアドバイスを何十種類も収集することになった。年の終わりには、身に付けていた無数のガラクタや小瓶、丸めた紙切れで、わたしの荷物ははちきれそうになっていた。それらの一つ一つが持つ効力は、それぞれに決められたタブー(禁忌)をわたしが守ることを前提としていた。これは、宗教・その他のいかなるシステムにおいても、多大な利益・恩恵の供給がその必要条件として、受益者に何らかの努力・徳を積むことをつねに要求するということの表れである。わたしにはすばらしい原則に思える。ただしわたし自身は、積むべき「徳」を限定せざるをえなかったが。 仮にわたしがお告げやタブーをすべて真に受けていたならば、飛行機を放棄することで既にやっかいなものになっていたわたしの一年は、さらにひどい混乱を来していたに違いない。インドネシアのある島の一人の黒魔術師bomohは、「何があろうと決して太陽に向かって小便をしてはならない」とわたしに告げた。またある者は、月に向かって小便をするなと言った。古代中国語で韻を踏みながら、二千年前の道教の賢者の声でわたしに語りかけたシンガポールの女シャーマンは、「犬と蛇の肉を二度と食べてはならない」と言った。ある占い師は牛肉を避けよと告げ、またある者はのこりの人生を厳格なベジタリアンとして過ごせと言った。ウランバトールのラマ教の老僧は、雌牛の糞を燃料とする炎であぶった羊の肩甲骨のひび割れ具合にわたしの運命を読んだあと、危険に襲われた際に使うようにとモンゴル草原の芳しい乾燥を一包み渡してくれた。我々が失神の際に用いる塩のようなものだ。プノンペン郊外の仏僧は、土地の癲癇患者たちが治療に使用している水で、わたしに着の身着のまま沐浴をさせた。(p16) 出会った占い師たちのほとんどは単に一風変わった人物たちであり、なにより生活の糧をえるための本職のペテン師もいくらか居た。だが、本当に特別な占い師たちも確かに居た。彼らは目の前の人間を判断する並外れた能力をそなえ、他人の心を読んだり、普通の人間には見えない「傷あと」を見いだすことのできる特別な精神的能力を持っていた。そうした幾人かの前では、彼らは本当になにか第六の感覚のようなものを持っているのではないかとわたしは考えたものだ。 そんなことがありうるのだろうか。かつては全ての人類があたりまえに持っていたある種の能力が、何千年もの時の流れの中で使われずにいるうちに失われてしまい、今ではごく僅かな者だけがその能力を保有しているというようなことが、果たしてありうるのだろうか。 世界の歴史は預言(予言)と奇跡にあふれている。だが特に欧米社会では、それらがすでに過去の物となってしまったかのような印象を受ける。ところがアジアでは、オカルトがニュースを解説するのにまだ役立てられている。少なくとも経済関係のニュースと、少し前まではイデオロギーに関しても。 中国やインド、またインドネシアでは、わたしたちが迷信と呼ぶものが今でも日々の生活に欠かせない存在である。占星術に手相術、人の顔や足の裏から、またはティーカップにのこった茶葉から将来を占う術は、民衆の生活、そして複数の国家の共通課題において重要な役割を果たしている。祈とう師による治療、シャーマニズム、それに風と水の術・風水とよばれる宇宙幾何学についても、同じことが言える。 アジアにおいては、子供の命名・土地の購入・株の取引・屋根のふき替え・出立の日取り、はたまた宣戦布告の日時にいたるまで、さまざまな決定がわたしたちのロジックとは似ても似つかぬ判断基準によって下される。数え切れない数の結婚が今でもそのようにして決められている。またあまたの建物がそうした基準によって設計され、建設されている。過去には、そもそも町全体が同じ方法で計画・建設されていた。さらには大小問わず、国民全体に関わる政治的決断の多くが、何らかの信仰か、多くのオカルト占術の一つの専門家の助言に拠るものとなっている。 はるか昔から人類は、おのれの人生の神秘に解釈を与えようとし、未来を読むための鍵を探しもとめ、自分の運命を支配することが出来ないものかと願ってきた。しばしば忘れられがちだが、中国語の漢字は人と人との間のコミュニケーション手段としてではなく、人が神にお伺いをたてる手段として生まれた。(p17)「隣の国への戦をわたしはするべきでしょうか、それともしてはならないでしょうか?」「この戦いにわたしは勝てるでしょうか、負けるでしょうか?」――王は平たい骨のうえにそう書かせた。そして、骨にうがたれた穴に真っ赤に焼けた鉄の針が通された。神の答えはその熱によって出来た骨のひび割れであった。すべてはそれを読み取ることが出来るか否かにかかっていた。骨の上に記された三千五百年前のそれらの文字こそが、現存する中国最古の文字であるとされている。 今でも、中国人、とくに東南アジアの華人たちは終わりをしらぬ質問の数々を彼らの神々に投げ掛ける。たとえば、大きなインゲン豆の形をした二つの木片を宙に投げることで、まさに天から、望み通りに正確な答えを得るという方法がある。答えは二つの木片の地面への落ち方次第であり、二つとも表向きか、二つとも裏か、表と裏それぞれかによって、「はい」、「いいえ」「もう一度試せ!」となる。 例の予言はわたしに、さまざまなメソッドの占術を探訪させ、いくつもの助言をあたえ、新たな認識の道を踏査させる機会となった。さらには、わたしが何度もその存在を直感し、かいま見、かすめたこともあるにもかかわらず、決して真面目に取り合ってはこなかったこの奇妙な神秘の世界をわたしに直視させる機会ともなった。 わたしのこの迷信をめぐる調査は、変わり続けるアジアに対する一つの反応のしかたでもあり、何世紀にもわたり、まさにそれが独特であったがために、西洋人を惹き付けてきた「神秘の東洋」の何がのこってゆくのかを観察する一つの方法でもあった。多くの新聞は、アジアが経済的ブームのまっただ中であり、来世紀はアジアの世紀であろうという。そしてその言葉が、超最新のコンピュータが書き出すグラフを通じて世界を見る銀行家や投資会社の社員たちを興奮させている。 だが現実には、経済の奇跡・アジアは、単なる幸福な成長をつづける大陸ではない。経済発展のスタンダード・モデルを追うことで、自らを殺しつつある世界でもあるのだ。そのモデルは彼らが選んだものではなく、今や人類のあらゆる行動を情け容赦なく支配しているように見える、かの利潤の論理が押し付けたものだ。 古い町がいくつも、没個性的な「近代的」住宅地をつくるために丸ごとつぶされてゆく。ビルマのジャングルの奥地、あるいはモンゴル草原の人里離れた小屋に至るまで、衛星を通じて外国から伝播してくる新しいモデルの耐えようがない圧力に、民族文化が丸ごと隅に追いやられている。マテリアリズムの恐ろしい波が今のところ何もかもを、そして全ての人々を圧倒している。(p18)にもかかわらず、深刻な混乱を生み出すこの傾向への反動なのか、アジアでは今、古い信仰やオカルト世界、伝統に根差した、その手のあらゆる奇妙な現象に対する興味が、若者を含め、人々の間で新たに沸き上がっている。 もしかしたら、これは全人類に普遍的な現象であるのかもしれない。人間関係がますます断片的なものとなり、日常生活からは自然がますます遠のき、あらゆる問題は科学によってのみ解決すべきものとされ、人の死が(かつてわたしが幼かった頃、まだそうであったように)心から体験されるものではなく、日々の暮らしから除外された、一つのタブーとしての色合いをますます強めている今という時代、人々は自分の運命の意味への確信を失いつづけており、その結果、慰めや同情、希望と友情をやみくもに探し求めるようになっているのだ。 異国情緒にあふれる東洋が、多くの欧米の若者たちを惹き付けるインスピレーションの源にふたたびなりつつあるのも、そのためなのかも知れない。故郷の学校でも、教会でも、いまや見つかりそうにもないある種の答えを、彼らはアジアの宗教やその修業生活のなかに探しにくる。東洋の神秘主義や仏教、アジアのグル(導師)たちは、我々の地のどんな教師・哲学者たちよりも優秀で、消費社会の牢獄・広告の爆撃・テレビの独裁体制から逃げ出したい者たちを手助けしてくれるように見えるのだ。 なにもかもが保障され、個人の欲望までが自分のものではない誰かの利益によって決定されているかのような、超管理社会からやって来て、スピリチュアルな東洋街道を歩き回る欧米の若者たちは増える一方である。 アジアを旅するうち以前にもわたしは、オレンジやスミレ色の仏僧の法衣を身にまとった西洋人の集団をなんども見たことがあったが、彼らの人生に興味を持ったことはなかった。だが今のわたしには、立ち止まり、彼らの話に耳を傾けるべき理由があった。わたしはこうして、わたしと同じくフィレンツェ出身でチベットの僧院で出家した元ジャーナリストや、バンコクの南にある寺で厳しい瞑想をつづける暮らしを選択した若いオランダの詩人などと知りあうことが出来た。二人とも、その手段は異なるが、いずれもわたしたちの時代の混迷の犠牲者である。 ヨーロッパでも、手相見・占星術師・予言者たちの項目がある電話帳の黄色いページがこれまでになく分厚くなっているのは、あきらかに同じ混迷が原因である。オカルト・ビジネスの客層も今では、かつてのようなだまされやすい哀れな女たちや少し頭の弱い者たち、孤独な人々や無知な者ばかりではない。これは今回の旅でわたしが発見することになった事実の一つだ。(p19)この一年を通じて、わたしのこの薄明の世界への好奇心が、実は多くの人々に共通するものであることも明らかになった。そんな世界には全く興味がなさそうに見える人々もそうであったし、普段はこの手の話題を口にしまいとする人々にしても、わたしの告白と、あたえられた予言を真に受けることにした決意を耳にして初めて心を開き、告白し、語り始めるのであった。ありきたりな話ではあるが、運命に幸運・不運の問題、それにどう対処すべきかという問いは、おそかれはやかれ、誰の胸にも浮かんでくるものなのである。 あとに続くページは、わたしのこの奇妙な旅の物語であり、つねに地に足をつけて過ごしたその一年の物語である……いやむしろ、かつてなく地に足がついてない一年の物語と言った方が良い。なぜなら、この十三ヶ月ほど翼なしに空を飛んで過ごしたことは、これまでなかったことだから。十三ヶ月の一年?その通りなのだ。まあ、それが最もふさわしい表現にちがいない。 それで、結果は? 「占い師に会いになんて、わたしは絶対行きません。なぜなら、人生に驚かされるのがわたしは好きだからです。」バンコクのある老婦人に、月に何回くらい占いに行くか尋ねたところ、彼女なりに謎めいたそんな答えをかえされたことがある。 わたしの場合、人生の驚異の数々に出会うことができたのは、一人の占い師のもとに行ったからこそであった。彼の予言はわたしに、新しい眼のようなものを開かせてくれた。予言は、そうでもなければ見ることもなかったであろう物事や場所、会うこともなかったに違いない人々をわたしに見せてくれた。おかげでわたしは前例の無い一年を、ラオスの象の背のカゴの中に座って始め、元CIA情報員のアメリカ人が指導する人里離れた仏教の修業地で瞑想用の座布団に座って終わることになった。 かの占い師の予言のおかげで、わたしはさらに……飛行機事故をひとつ免れた。1993年の3月20日、カンボジアで15人のジャーナリストをのせた国連のヘリが墜落した。その15人のなかには、わたしの代わりに乗ったドイツ人の同僚がいたのだ。 |